9月も2周目が終わりました!
【月刊】に引き続き【週刊】パパの片頭痛ダイアリーもはじめました。
- 【週刊】片頭痛ダイアリーでは、一週間の気圧と頭痛レベルの関係グラフで、気圧と頭痛の関係をパッとみてわかるようにしてみました。また、片頭痛ダイアリーと見比べることで、片頭痛が発生する時の傾向を探ります。
- 【月刊】片頭痛ダイアリーでは、主に数字(頭痛の発生回数・薬の服用回数)を観察し、自分の片頭痛は良くなっているのか?現状維持なのかを観察します。
それでは【週刊】パパの片頭痛ダイアリー(vol.1)、まとめてみようと思い※引用:頭痛ーる(ベルシステム24)よります!
今週の【気圧と頭痛の関係グラフ】(2025年9月2週目)
8月から、頭痛アプリ頭痛ーる(ベルシステム24)で気圧を確認しています。
その気圧の結果と、片頭痛ダイアリーの記録を1つの表にまとめてみました。👇️
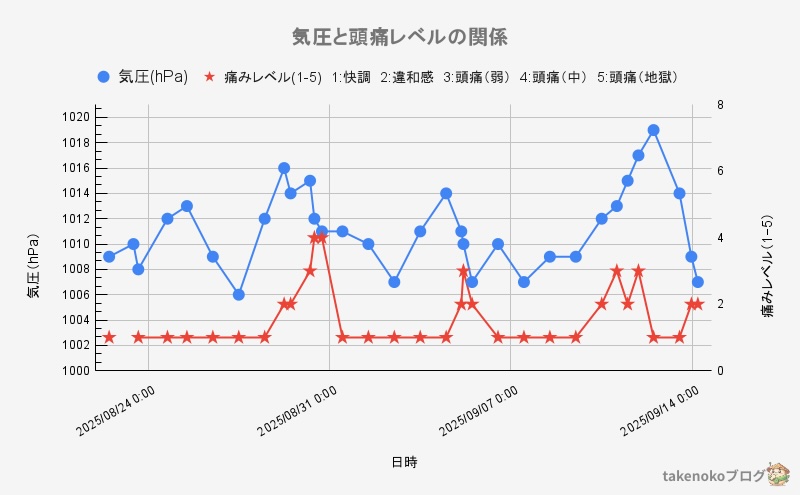
まだ3週間くらいの表ですが、こうして見てみると、パパの頭痛に1つのパターンがあることがわかりました。
★気圧が上がってから下がり始めた時に頭痛が悪化する傾向がある。
(データが少ないので仮説ですが、表を見た感じではそのように読み取れます。)
気圧と頭痛の関係グラフを使うと、片頭痛ダイアリーだけではわからなかった頭痛発生時の特徴が見得てきました。これは良い発見でしたので、今後も気圧と頭痛の関係グラフと片頭痛ダイアリーを並行して記録していこうと思います🤞💡
今週の【片頭痛ダイアリー】(2025年9月2週目)
いつものパパの片頭痛ダイアリーでは、ダイアリーを3日分くらいを載せていますが、
【週刊】では、1週間分を載せます。
生活リズムの乱れなどがないか、無理していないかなど、生活環境の振り返りができるのではないかと思います。
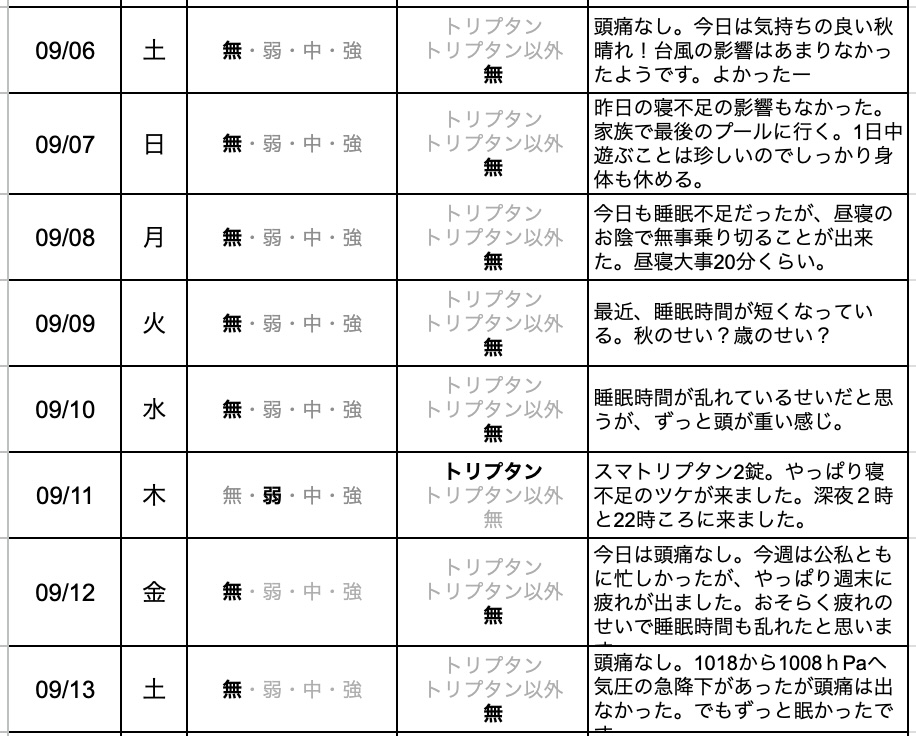
今週の片頭痛の回数と傾向(9月2週目)
<片頭痛の総発生回数 :2回(スマトリプタン2錠) >
(内訳↓↓)
- 違和感・予兆 :4回(頭が重い・首肩のコリ)
- 弱 :2回(スマトリプタン2錠)
- 中 :なし
- 強 :なし
今週、特徴的だったことは、深夜2時ころに目が覚めて眠れなくなることが数回あったこと。
特に大きなストレスがあった訳では無いけれど、仕事が忙しかったからか?それとも、急に秋らしくなってきて夜の気温が下がってきたからか?
この寝不足が原因かはわかりませんが、木曜日には片頭痛が2回襲ってきました😱
気圧のグラフを観ると、大きな気圧の上昇があった日なので、気圧が原因とも考えられます。
おそらく、寝不足による生活リズムの乱れ&気圧の変化が重なって頭痛が出たのではないかと思います。
今週の服薬記録
今週は頭痛時にスマトリプタンを合計2錠使用。
木曜日の早朝4時と夜の10時に飲みました。
一度良くなったと思って、早めに就寝したら、珍しく夜の10時ころに頭痛で目が覚めました。
原因と思われる要因の振り返り
- 頭痛が2回出た木曜日は、大きな気圧の変化があった日でした。
(ちなみに、ヘン友(片頭痛友だち)は頭痛がひどく仕事を休みました。相当ひどかったようです😢) - 頭痛の前日・前々日は深夜に目が覚めてしまい、生活リズムも狂っていました。
- 大きな気圧の変化がある時は、ヘン友と頭痛が重なります。⇐この事実に気付いてから、気圧と頭痛の関係を確信しました。(パパの頭痛の場合)
来週の片頭痛予防
やっと涼しくなってきました。秋らしくて嬉しいです。
その反面、朝方は少し寒く感じることもあります。
子供達は早速くしゃみをしてる。キケン🤧
こまめな体温調節をして風邪予防に努めようと思います!
秋の気候は大好きなのですが、私にはアレルギーがあります。
・ブタクサ
・稲系
・ダニ
・ハウスダスト
この2つの花粉による咳や喉のかゆみ(アトピー咳嗽)が強く出ます。
頭痛が出た時に咳やくしゃみが出ると最悪です。
アレルギーの予防は難しいですが、基本的な体調管理はしっかりしていこうと思っています。
来週は、気圧が下降する時の頭痛予防について調べてみようと思います!
週末に向けて、気温がだいぶ下がってくるようです。
皆さんも季節の変わり目、体調を崩されませんようお気をつけ下さい。
秋の味覚・行楽たくさん楽しみたいですね🍎🐟️🍄
柿とモンブランと秋刀魚ときのこ汁食べたいな〜〜〜〜
では、引き続き良い3連休をお過ごし下さい☺️✨️
※この記事は筆者の個人的な体験をもとに記録したものです。薬の服用や治療法に関しては、必ず医師・薬剤師の指導を受けてください。



コメント